「私的な部分からいくと、自費で何度も東京の陸運局に足を運んでいるんだね。」
お話は、庄蔵氏の町への関わり方から始まりました。それは、ちりめん街道のある加悦地区にとって最も大きな歴史である「加悦鉄道の敷設」そして「丹後大震災」に関するくだりです。
「鉄道(の敷設)が成功するまでの間、何度も東京に行っていた。けど、独断専行はしなかった。細井直義、市田力蔵…地域の有力者を参謀につけていたんだね。震災(丹後大震災)の頃も、有力者連中を呼び集めて、鉄道の敷設について事細かに進めていたみたいだね」
加悦地区では大正15年、地域住民823名の出資によって、約5.7kmの鉄道が敷設されました。そもそも住民が自らの手で鉄道を敷いた歴史そのものが異例です。そして、そのうちの大口出資者の一人が、庄蔵氏だったというわけです。
たったこれだけの情報でも、庄蔵氏がどのようなリーダーシップをとっていたのかが伺えます。少なくともワンマンではなかったこと、鉄道の敷設を成功させるために、400km以上離れた東京まで自費で通い続けていたこと。そして有力者でありながら、強引なやり方はしなかったのです。
私は、じんわりと熱い思いが胸に湧き上がるのを感じました。町を牽引する力を持ちながらも、他者との連携を欠かさない生き方に、どこか理想のリーダー像のようなものを垣間見たのです。さらにその人物の眼差しは、この町のみならず世界に向けられていたことが分かりました。
「尾藤家にある金庫には、満州鉄道の株券がたくさん入っていた。つまり小さな田舎の経済だけではなくて、日本全体の経済の動向や、国の動向にも関わっていたみたいだね。日本が世界に進出しようとしていたとき、世界の情勢も読み取って投資している。人物が大きい。」
小野住職は庄蔵氏をこう表現しました。「気宇壮大」。こういった人物の人並外れた構想の大きさと将来像が、当時の加悦地区を支えていたのでしょう。
また小野住職は、こんなお話も付け加えてくださいました。
「与謝峠下に、大江山鬼嶽稲荷の鳥居と、きつね姿の狛犬がある。たしか大正8年に庄蔵さんが発起人になって、町内外の人に呼びかけて奉納されたものだった。」
ご住職はさらに続けます。片方で近代文明の象徴である鉄道の敷設を考えながら、片方では農耕の神さんへの信心を深めようという気持ちがあった…。つまり心の問題、町の人々の精神の涵養にも意を用いたと言えます。
このお話はどこか、英雄を中心に描かれた映画を見ている時の感覚でした。力強く、勇気付けられる。しかし不思議なもので、それだけでは人間臭さのようなものが感じられず、まさに「映画の中の人物」のようで現実味が生まれてこないのです。

11代庄蔵氏をはじめ、多くの有力者が尽力し、住民たちの出資によって敷設された私鉄加悦鉄道。写真は昭和30年代の様子。
ところがその「現実味」に触れるエピソードが小野住職から語られ、私は思いがけず暖かい気持ちになれたのです。
「息子の卓造さんを、京都の松葉元という旅館*に呼んで、一緒に食事をしたということを、日記に細かく書いてる。(庄蔵氏は)京都経由で東京に行っていたんだね。楽しげな雰囲気が手帳からうかがえる」
庄蔵氏は自身の日記が書かれた手帳を(何冊も)残しています。そこには、「卓造来る」というフレーズがしょっちゅう登場するらしいのです。
「子煩悩っていうかね、そのあたりは普通の「親父」だったんだね」
庄蔵氏には4人の子供がいましたが、男性はただ一人、卓造さんだけでした。一つの町を支える豪商は、同時に息子との会食を楽しみにしていた父親だったのです。
また小野住職は「これは(私の)父親が言っていたんだけどね」と、続けます。庄蔵氏の娘さんがお見合いをしたときのこと、彼は終始落ち着かない様子だったそうです。
父親としてはうまく縁談が進んで欲しいと願うのは当然です。それを思うといてもたってもいられない心情があったのだろう、と小野住職は語ります。そういった場でそわそわする様は、豪商というイメージからは想像もつかない、なんとも微笑ましいエピソードです。
当時は男女格差が激しく、庄蔵氏も妻のつるさんが自分より高い場所からものを言うことがあると叱り付けるような人物だったそうです。例えば、畳の間にいるつるさんが土間にいる庄蔵氏に話しかけた時など…それは私たちがイメージする当時の「男性像」そのものです。厳しくもあり、一方で子煩悩でもある、人間的な一面を感じます。

左上が卓造さん。11代庄蔵氏の4人の子供のうち、男の子は卓造さんだけだった。卓造さんは後に12代庄蔵を名乗る。


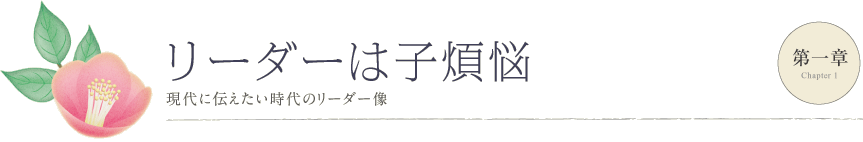

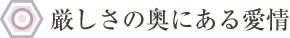
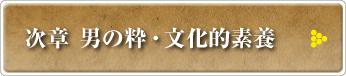
 〒629-2403 京都府与謝郡与謝野町字加悦1060 旧加悦町役場内 FAX 0772-43-0159
〒629-2403 京都府与謝郡与謝野町字加悦1060 旧加悦町役場内 FAX 0772-43-0159